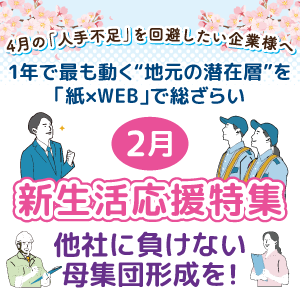2025年7月11日
労務・人事ニュース
主要6港で121万TEU超を記録、令和7年4月の貿易回復が人材需要を後押し
エラー内容: Bad Request - この条件での求人検索結果表示数が上限に達しました
港湾統計速報(令和7年4月分)(国交省)
令和7年4月における日本の主要6港、すなわち東京港、川崎港、横浜港、名古屋港、大阪港、そして神戸港における外国貿易貨物のコンテナ取扱量は、前年比で2.9%増加し、合計1,212,782TEUに達しました。この数字は、グローバル経済の影響を受けながらも、国内港湾物流が堅調に推移していることを裏付けています。特に注目すべきは、輸出が609,481TEU、輸入が603,301TEUといずれも前年同月を上回る結果である点です。これは国内製造業の安定供給体制と、消費者需要の回復を反映したものと考えられます。
東京港は、全体で375,694TEUを記録し、前年同月比で5.3%の伸びを示しました。輸出は169,705TEUで5.6%増加、輸入は205,989TEUで5.0%増と、国内最大の港湾としての役割を強く印象づける結果となりました。これに次ぐ横浜港では、240,729TEUが取り扱われ、前年比3.2%増となり、特に輸入においては5.0%増の109,815TEUを記録しています。首都圏に近いこれらの港が共に安定した成長を見せていることは、企業が安心してサプライチェーン戦略を構築できる環境にあることを意味します。
また、名古屋港では輸出が120,925TEU、輸入が105,511TEUと、いずれも前年同月比で増加を示しており、自動車産業をはじめとする製造拠点の活発な輸出入活動が見て取れます。大阪港においても、総コンテナ個数は179,935TEUで前年比4.1%増、輸出は84,419TEU、輸入は95,516TEUと堅調な数字を維持しています。これらの数字は、関西圏の産業活動の底堅さを物語るものです。
一方で、神戸港と川崎港においては、前年同月比でそれぞれ3.5%減、24.0%減という結果となりました。神戸港では輸出入ともに減少し、輸出が100,449TEUで2.4%減、輸入が82,828TEUで4.9%減でした。川崎港に至っては、輸出が3,069TEUで33.1%減、輸入が3,642TEUで14.1%減と、大きく落ち込みました。このような港の動向は、地域経済の影響や港湾設備の更新状況、あるいは航路の見直しといった外部要因による影響も考えられ、企業が物流戦略を再構築する際の判断材料となるでしょう。
全体的に見れば、主要6港の合計で前年比2.9%の増加という結果は、わが国の貿易活動がコロナ禍から回復し、国際的な物流需要の再拡大を受けて順調に推移していることを示しています。採用担当者にとっては、これらの数字が意味するのは単なる物流の増減ではありません。それはすなわち、サプライチェーンの安定性、製造・流通業における業務需要の増大、ひいては採用活動の強化が求められる状況の到来を意味しています。コンテナ取扱量の増加は、物流や通関、輸出入業務、そしてそれらを支える情報システムの分野における人材ニーズの高まりと直結しており、今後の採用活動の重要な判断材料となり得るのです。
また、港湾別の詳細データに目を向けることで、特定の地域における物流の強みや課題が浮き彫りとなります。東京港や横浜港のように、着実な成長を遂げている地域は、人材投資の重点拠点とする価値があり、逆に川崎港のように取扱量が減少している港については、将来的な再編の可能性や他港へのシフトも検討する必要があるかもしれません。こうした数値から読み取れる市場動向を的確に捉えることが、今後の経営判断や採用方針において極めて重要になります。
⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ