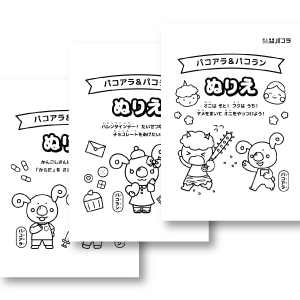2025年4月13日
労務・人事ニュース
令和5年度 携帯契約数が2億2,192万件に到達、固定電話は1,183万件に減少
- 歯科衛生士 車通勤OK!社保完備!予防にしっかり取り組める!教育制度がしっかりしてる
最終更新: 2026年2月1日 21:30
- 歯科衛生士 社保完備 訪問を学べます 経験は問いません
最終更新: 2026年2月1日 21:30
- 歯科衛生士 経験の浅い方も大歓迎!安心の高待遇と万全のサポート体制でお待ちしております
最終更新: 2026年2月1日 21:30
- 歯科衛生士 非常勤衛生士募集中 開業から20年。歯科医療を通して患者さんの健康をサポートしています
最終更新: 2026年2月1日 21:30
通信量からみた我が国の音声通信利用状況 ―令和5年度の利用状況―(総務省)
令和5年度における日本国内の音声通信利用状況に関する統計が総務省から公表され、通信業界のみならず多くの業界関係者にとって注目すべき内容となっています。本統計は、電気通信事業報告規則に基づいて全国の通信事業者から報告されたデータを集計・分析したもので、携帯電話やIP電話、加入電話、公衆電話など多様な通信手段の利用動向が明らかになりました。特に契約数の推移、通信回数や通信時間の変化からは、社会構造の変化や働き方の多様化、さらに企業活動の通信インフラ依存度が一層高まっている現実を映し出しています。
まず注目すべきは、移動系通信(主に携帯電話)の契約数が令和5年度末時点で2億2,192万契約に達し、前年から5.3%の増加となった点です。これは日本の総人口を大きく上回る数字であり、個人の複数端末保有や法人契約の増加を反映していると考えられます。特にスマートフォンの普及とビジネスユースでの通信ニーズの拡大が背景にあり、今後も業務連絡やモバイルワーク、業務アプリの使用に不可欠な通信基盤としての役割は一層重要になっていくでしょう。
一方、固定系通信に分類される加入電話やISDN、公衆電話の契約数は軒並み減少傾向にあり、全体で1,364万契約・台と前年比7.9%の減少が見られました。中でもISDNは170万契約で、前年比11.7%という急激な減少を記録しています。かつては企業の代表電話やFAX回線として欠かせなかったISDNがこのように減少している背景には、IP電話への移行やクラウド電話サービスの普及、デジタル化の進展があります。企業の通信インフラも固定型から柔軟なIPベースへと確実に移行しており、この動きは採用活動におけるリモート対応力や柔軟な勤務環境の構築にも直結しています。
IP電話の利用番号数は4,569万件と前年度と同水準を維持しており、通信コストの削減や業務効率化の観点から、特に中小企業を中心に安定した需要が見込まれています。IPベースの電話システムは在宅勤務やクラウドPBXの導入にも適しており、テレワーク制度を整備する企業では採用候補者に対する働きやすさのアピールポイントともなっています。こうしたデジタル通信環境の整備状況は、今後の人材確保競争において無視できない要素となるでしょう。
通信回数全体に目を向けると、令和5年度の総通信回数は602.4億回で前年比6.6%の減少となり、通信時間も2,511.5百万時間と前年比11.0%の減少となりました。この減少傾向は、音声通話よりもチャットやビデオ会議、SNSといった非通話型コミュニケーション手段の浸透を反映しており、ビジネスシーンでもSlackやTeams、Zoomなどの利用が定着していることが背景にあります。こうしたコミュニケーション手段の変化に柔軟に対応できる人材や、ITツールを使いこなせる職場環境の整備が企業には求められています。
発信手段別では、固定系発信が73億回で前年比13.3%減、IP電話が151億回で3.8%減、携帯電話・PHS発信が378.5億回で6.3%減となりました。全体の通信回数に占める割合では、携帯電話・PHSが62.8%と最も多く、IP電話が25.1%、固定系が12.1%と続きます。この構成比からも、モバイル中心の通信環境が主流となっている現状がうかがえます。また、通信時間でも携帯電話・PHSが1,893百万時間で全体の75.4%を占めており、企業活動においても携帯電話を中心としたモバイル環境への最適化が進められていることが分かります。
相互通信の観点では、携帯電話・PHS同士の通信が全体の46.1%を占めており、通信時間ベースでは59.6%と過半数を超えています。これは社内連絡や顧客対応など、携帯電話を介したコミュニケーションの比重が非常に高いことを示しており、モバイルデバイスの管理体制やセキュリティ対応を含めたモバイル戦略の構築が重要です。採用面でも、モバイルワークに即した業務設計や、場所にとらわれない働き方を提示できるかが、応募者からの評価に直結する時代になっています。
また、国際電話トラヒックについては通信回数が1,033.3百万回と前年比34.1%の大幅な増加を記録しました。通信時間は612.1百万分で5.4%の減少となったものの、海外との接点が増えている傾向は明確であり、グローバル展開を進める企業にとっては多言語対応や海外通信インフラへの対応力が問われる状況です。国際間の通信回数のうち96%が着信であるという特徴もあり、国内企業が海外からの連絡に迅速に対応できる体制の構築が今後ますます重要になります。
これらの通信データの変化からは、企業が採用活動を行ううえでも、通信環境の整備状況や働きやすさに対する配慮が求職者から厳しく見られているという事実が浮かび上がります。固定電話の減少とモバイル、IPベースへの移行は単なる技術の変化ではなく、職場環境そのものの柔軟性を象徴しており、採用競争を勝ち抜くうえで企業文化や業務環境の整備が鍵となっているのです。
ここで紹介したデータから、企業の採用担当者が注目すべきポイントを数字に基づいて可視化し、今後の人材獲得戦略の材料として活用していただければと思います。
⇒ 詳しくは総務省のWEBサイトへ