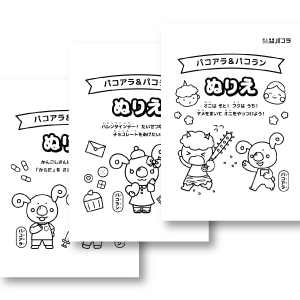2025年4月18日
労務・人事ニュース
全国1,069校を調査!大学入試の選抜方法と評価制度の実態
エラー内容: Bad Request - この条件での求人検索結果表示数が上限に達しました
大学入学者選抜の実態の把握及び分析等に関する調査研究(文科省)
令和6年度に実施された全国の大学および短期大学を対象とする入学者選抜に関する調査では、国内全1,069校から100%の回答を得ており、そのデータの信頼性と網羅性は非常に高いものです。この調査は、大学がどのような体制で選抜を行い、どのような方法を用いて入学者を評価しているかを詳細に分析したものであり、教育現場だけでなく、将来的に学生を採用する企業にとっても貴重な情報が多数含まれています。
まず、大学入試における選抜方法として最も多く用いられているのは「一般選抜」で、全選抜区分のうち約40.9%を占めました。次いで「学校推薦型選抜」が26.7%、「総合型選抜」が19.3%と続いています。これら3つの方式で全体の約87%を構成しており、現在の入学者選抜の主流であることが明確になりました。
興味深い点として、学校推薦型選抜における「公募型」の導入状況が挙げられます。国立大学では99.2%、公立大学では90.2%が公募型を採用しており、特定の高校に偏らない公平な募集が進められています。一方、私立大学では22.3%と低く、多くが指定校推薦や附属校推薦といった形式をとっており、その選抜方針には大きな違いが見られます。なお、私立大学における指定校推薦の91.7%は「専願(他大学との併願不可)」であるのに対し、公募型は55.4%が「他校併願可」となっており、受験生の選択肢を広げる動きが見て取れます。
選抜方式におけるデジタル化の進展も顕著です。電子出願が可能な選抜区分は、一般選抜で98.2%、総合型選抜で85.4%、学校推薦型選抜では81.7%となっており、ほとんどの大学がオンラインでの受験申請に対応していることがわかります。これは受験生の利便性向上だけでなく、大学側の業務効率化やデータ管理の一元化にも寄与しています。
また、大学入学共通テストの活用状況も分析されています。国立大学では96.2%、公立大学では98.5%が共通テストを合否判定に利用しており、私立大学でも44.5%が採用していることがわかります。特に注目すべきは、共通テストを利用する私立大学の選抜区分のうち、数学を「必須科目」としているのが35.0%、国語を「必須」としているのが43.5%であり、文理を問わずバランスの取れた基礎学力が求められている点です。
さらに、大学側が実施する「個別学力検査」に関しては、国立大学の68.5%、公立大学の52.6%、私立大学の59.3%が実施しており、英語・数学・国語の3科目が主に出題されています。特に英語については、一般選抜の87.4%が必須または選択科目として設定しており、グローバル化を背景に語学力の重視が進んでいることがうかがえます。
入学者選抜の公平性・公正性確保に関する取組も、今後の教育改革の一助となる情報です。合否判定に関しては、99.1%の大学が合議制の会議体で決定しており、評価の透明性を確保する努力がなされています。また、98.6%が複数人による採点・確認を行い、77.3%が小論文や面接に関する評価マニュアルを整備しているなど、選抜の妥当性と客観性を確保するための体制整備が進んでいます。
一方で、個別学力検査の「問題と解答」の公表状況にも大きな変化が見られます。国立大学では95.1%、公立大学で88.8%、私立大学では92.8%が問題を公表しており、解答の公表についても8割以上が対応済みです。これは受験生への情報提供の透明性を高め、大学入試に対する信頼性を向上させる要素となります。実際、公表方法としては、国公立大学では大学ホームページ上での掲載が主流であり、私立大学では希望者への配布や問題集としての掲載が多くなっています。
成績の開示制度についても注目すべき点が多くあります。国公立大学は100%が制度を設けており、私立大学でも64.2%が成績開示に応じていることがわかりました。開示の方法では、郵送または電子媒体での送付が49.2%と最も多く、次いで大学窓口での閲覧(29.1%)、希望者への配布(24.0%)が続いています。これは受験生本人の納得感を高めると同時に、次年度以降の学習改善にも役立つ重要なフィードバックの機会となります。
最後に、大学の広報活動の取り組みにも触れておきましょう。オープンキャンパスの実施率は全体で99.9%と非常に高く、入試説明会(89.4%)や高等学校訪問(98.1%)も積極的に行われています。私立大学ではさらに、ソーシャルメディアの活用が94.7%に達しており、受験生との接点を多様化させる試みが広がっています。実際に、学生確保に最も貢献している広報活動として「オープンキャンパス」が全体の80.8%で最も多く挙げられており、リアルな体験を通じて大学の魅力を伝えることの重要性が改めて示されました。
このように、入試制度は単なる試験の枠に留まらず、大学と社会の接点を担う重要なインフラとして機能しています。企業の採用担当者にとっても、どのような選抜過程を経て学生が大学に進学しているのかを把握することは、人材のバックグラウンドを理解するうえで有益です。今後も、教育と社会の接続がよりスムーズに行われるよう、制度の透明性と公正性の維持・向上が求められていくでしょう。
⇒ 詳しくは文部科学省のWEBサイトへ