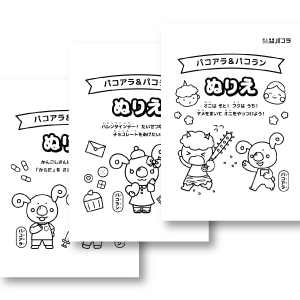2025年8月1日
労務・人事ニュース
主食用米の作付意向が前年比10.4万ha増、735万トンの生産見込みで過去5年最大を記録(令和7年産第3回中間的取組状況(6月末時点))
- 歯科衛生士 週休3日制 社保完備 プライベートの充実もスキルアップも実現できる
最終更新: 2026年2月1日 21:30
- 歯科衛生士 うれしい週休2.5日 午前のみのお仕事OK!残業なし!有給休暇・長期休暇あり!ライフスタイルに合わせて働くことができる歯科医院
最終更新: 2026年2月1日 21:30
- 歯科衛生士 「大人になっても変わらぬ笑顔でいるために」小児歯科専門の医院
最終更新: 2026年2月1日 21:30
- 歯科医師 あなたがいつも笑顔で働けて成長できる環境をご用意しています
最終更新: 2026年2月1日 21:30
水田における作付意向について(令和7年産第3回中間的取組状況(6月末時点))(農水省)
農林水産省が2025年7月18日に公表した「令和7年産の水田における第3回中間的取組状況(6月末時点)」によれば、日本全国における主食用米の作付意向が顕著に増加していることが明らかになりました。この報告は、農業再生協議会が地域ごとの需要動向を踏まえてまとめたものであり、生産者や産地が主体的に作付けを判断できる環境の整備を目的としています。令和7年6月末の時点における調査結果をもとに、今後も取組計画書の修正提出が可能であることから、今回の数値はあくまで中間的な意向としての位置づけとなっています。
まず、最も注目すべきは主食用米の作付面積の増加傾向です。全国の作付意向面積は136.3万ヘクタールとなっており、前年から10.4万ヘクタール増加しました。これは過去5年間において最大の作付面積であり、生産量も735万トンと推計されています。対前年では56万トンの増加にあたり、これもまた過去最大の増加幅となっています。さらに、令和7年4月時点の前回調査と比べても、2.9万ヘクタール、16万トンの増加が見込まれており、生産の意欲が全国的に高まっている様子がうかがえます。
一方で、戦略作物に関しては軒並み作付意向が減少しており、農業政策の転換点ともいえる状況が浮かび上がっています。加工用米は4.4万ヘクタールで、前年比0.6万ヘクタールの減少となりました。新市場開拓用米、つまり輸出用などの新たな需要を狙った米は0.9万ヘクタールと、こちらも0.2万ヘクタール減少しています。さらに、米粉用米は0.4万ヘクタールで前年比0.3万ヘクタール減、飼料用米は4.9万ヘクタールで前年比ちょうど半減となる4.9万ヘクタールの減少、WCS用稲、すなわち稲発酵粗飼料用の稲も5.0万ヘクタールと、前年から0.7万ヘクタールの減少が見られました。これらの戦略作物の減少は、主食用米の需要回復や価格安定を受けた作付けの再集中の動きと見られています。
加えて、麦の作付意向も9.6万ヘクタールと、前年から0.7万ヘクタール減少しており、大豆も7.6万ヘクタールで前年比0.9万ヘクタールの減少となっています。麦や大豆は自給率向上の観点から重視されてきた作物であり、これらの減少は農業政策全体に影響を及ぼす可能性も否定できません。こうした作付意向の動向は、農業経営だけでなく、農業機械メーカー、種苗業者、流通業者などの周辺産業にも広範な波及効果を及ぼすため、各業界においても注意深く分析することが求められます。
都道府県別に見ても、主食用米の増加傾向は全国的であり、例えば北海道では前年の83.7万ヘクタールから90.3万ヘクタールへと6.6万ヘクタールも拡大しました。秋田県では72.2万ヘクタールから81.1万ヘクタールへと8.9万ヘクタールの増加となり、東北地方を中心に積極的な生産拡大が見て取れます。こうした動向は、気象条件や農地の集積化、労働力の確保状況、さらには政策支援の活用度合いなど、複数の要素が複雑に絡み合って形成されています。
企業の人事・採用担当者にとって、今回の報告から読み取るべき重要な示唆は、農業における労働需要の変化と地域経済への影響です。特に主食用米の作付増加は、季節労働者や地域雇用の拡大を促す可能性があり、農業を主要産業とする地域においては、若年層や移住者の新規就農支援などと組み合わせた人材施策の構築が期待されます。一方で、戦略作物の減少は加工業や飼料業界にとっては原料確保の課題となり、それが工場運営や商品供給体制に影響を及ぼす懸念もあります。
また、農業分野の動向は食品業界や物流業界、さらには環境政策とも密接に関連しています。主食用米が増加傾向にあることで、市場における米価格の安定が期待される反面、需要過多に陥れば価格の下落を招くリスクもあるため、流通量のコントロールと在庫管理の体制強化が不可欠です。このように、作付意向という一見限定的な情報も、全体のサプライチェーンに広がる波紋を正確に把握することが、企業活動の安定に繋がります。
農業政策の方向性としては、主食用米を基盤にしながらも、付加価値の高い新市場開拓用米や米粉、飼料用などの多様化戦略が引き続き求められる局面にあります。その中で、加工業や外食産業との連携を図り、需要側のニーズを積極的に取り込む姿勢が重要です。これにより、農業と産業界が一体となった持続可能な食料供給体制の構築が現実的な選択肢となっていくでしょう。
最終的に、2025年6月末時点で示されたこれらの作付意向は、農業従事者の意識変化を反映しているだけでなく、国全体の食料安全保障や地域活性化にもつながる重要な指標となっています。
⇒ 詳しくは農林水産省のWEBサイトへ