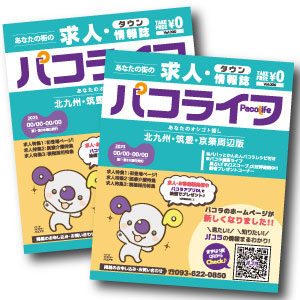2025年5月19日
労務・人事ニュース
全国58エリアで運用開始、熱中症警戒アラートが4月23日から10月22日まで稼働
- 1人でモクモク作業 年間休日120日以上 家具家電つき寮完備 WEB面接 工場ワーク
最終更新: 2026年1月21日 16:28
- 1人でモクモク作業 年間休日120日以上 家具家電つき寮完備 WEB面接 工場ワーク
最終更新: 2026年1月21日 16:28
- 1人でモクモク作業 年間休日120日以上 家具家電つき寮完備 WEB面接 工場ワーク
最終更新: 2026年1月21日 16:28
- 1人でモクモク作業 年間休日120日以上 家具家電つき寮完備 WEB面接 工場ワーク
最終更新: 2026年1月21日 16:28
令和7年度「熱中症警戒アラート」の運用開始について(気象庁)
2025年4月15日、気象庁と環境省は令和7年度の「熱中症警戒アラート」の全国運用を発表し、同年4月23日から10月22日までの6か月間にわたり、全国58の府県予報区単位で実施されることが明らかになりました。このアラートは、熱中症のリスクが著しく高まると予測される際に、地域住民や関係機関へ向けて「暑さへの気づき」を促し、熱中症による健康被害を未然に防ぐための対策行動を呼びかける目的で設けられています。
発表の基準となるのは、暑さ指数(WBGT)が33を超えると予測された場合です。WBGTとは、気温だけでなく湿度や日射量(輻射熱)、風速など複数の要素を組み合わせた総合的な指標で、熱中症の危険度を評価するために用いられています。気象庁と環境省は、府県予報区内に設定された算出地点のいずれかにおいて、翌日の日中にこの指数が33を上回ると予測される場合、前日の夕方5時頃および当日朝5時頃に該当エリアへアラートを発表します。
この制度は令和3年度から本格導入され、発表回数は年々増加傾向にあります。令和3年度には613回、令和4年度には889回、令和5年度には1232回、そして令和6年度には1722回と過去最多を記録しました。これは気候変動による猛暑日数の増加や高湿度化が背景にあるとされており、今後も熱中症リスクへの備えは一層求められることが予測されます。
また、令和6年度からは「熱中症特別警戒アラート」も新たに導入されています。これは、過去に例のない極端な高温が広域的に予測される場合に発表されるもので、WBGTが35を超えると見込まれる時点での発表が想定されています。対象地域内のすべての情報提供地点において、この数値が達すると予測される場合に発表されることとなっており、現時点では運用は開始されているものの、過去に発表された実績はまだありません。しかし今後の気候状況によっては、全国的な暑さ警戒体制の一環として、運用の機会が訪れることも想定されています。
このようなアラート制度の強化は、行政や医療関係者だけでなく、企業活動にとっても重要な意味を持ちます。たとえば建設業や運輸業など、屋外での作業が多い業種においては、従業員の健康管理と労働安全の観点から、これらのアラート情報を迅速かつ的確に活用する体制の整備が求められています。また、製造業でも工場内の温湿度管理や作業スケジュールの調整に関わる判断材料として、WBGTの情報は極めて有用です。
小売業やサービス業においても、アラート発表日には冷却グッズや飲料の需要が急増する傾向があり、販売戦略の策定や在庫管理に大きく関わってきます。特に高齢者施設や保育施設など、熱中症リスクの高い人々を対象とした施設を運営する企業にとっては、アラートの発表は直接的に業務オペレーションや利用者の安全管理に直結する問題です。
さらに、企業の採用や人材戦略の観点でも、気候リスクは新たな評価軸として浮上しつつあります。たとえば、全国に支店や工場を持つ企業では、地域ごとの気候傾向や熱中症リスクに応じて人材配置を考慮したり、作業環境の安全基準を地域ごとに調整したりする必要があります。こうした中、熱中症警戒アラートは単なる気象情報にとどまらず、企業全体の持続可能な成長を支えるためのリスク管理ツールとしての役割を担っているのです。
また、気象庁と環境省は「環境省熱中症予防情報サイト」にて、アラートの発表状況をリアルタイムで公開しており、誰でもアクセスして確認できる体制を整えています。これは情報の透明性を高め、迅速な対応を可能にする点で非常に有効な仕組みといえます。企業においては、このサイトを活用して社内の気象リスク管理を行うほか、社員への教育や研修に取り入れることも効果的です。
⇒ 詳しくは気象庁のWEBサイトへ