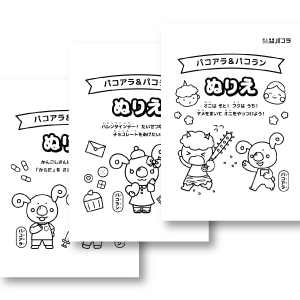2025年7月18日
労務・人事ニュース
単独世帯が1899万世帯に到達、全世帯の34.6%に拡大した社会の変化(令和6年)
- 歯科衛生士 残業ほぼゼロ 訪問診療も学べる!働きやすい環境で「歯科衛生士力」を活かしませんか
最終更新: 2026年2月1日 21:30
- 歯科衛生士 車通勤OK しっかり勉強できる 週休2.5日でゆとりのある勤務体制です
最終更新: 2026年2月1日 21:30
- 歯科衛生士 シフト相談しやすい各々に合わせた働き方が叶う、長期勤務されている方が多い働きやすい医院です
最終更新: 2026年2月1日 21:30
- 歯科衛生士 駅近で通勤に便利 社会保険完備で安心して働けます
最終更新: 2026年2月1日 21:30
2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況(厚労省)
2025年7月4日現在、厚生労働省が発表した「2024(令和6)年国民生活基礎調査」の結果は、日本社会の構造変化と国民の暮らしの実情を如実に示す重要なデータとなっています。調査は全国約6万1千世帯を対象に行われ、所得票では約5千世帯のデータが集計されました。本調査の主な目的は、保健、医療、福祉、年金、所得といった国民生活の基本的側面を把握し、今後の厚生労働行政の政策立案に必要な基礎資料を提供することにあります。
今回の調査により、単独世帯は1899万5千世帯にのぼり、全体の34.6%を占めることが明らかになりました。これは調査開始以来、世帯数・割合ともに過去最高となっており、核家族化や高齢化社会の進行を象徴する数字です。特に高齢者世帯は1720万7千世帯、全体の31.4%に達し、こちらも過去最高の値となっています。反面、児童のいる世帯は907万4千世帯で全体の16.6%にとどまり、こちらは過去最少を記録しました。子育て世代の減少や出生率の低下が影響していると考えられます。
65歳以上の者がいる世帯は2760万4千世帯で、全世帯の50.3%と過半数を占めました。うち最も多い構成は単独世帯で903万1千世帯に及び、全体の32.7%を占めています。高齢者単独世帯のうち、男性は36.0%、女性は64.0%となっており、性別による単身化の偏りも顕著に表れています。特に女性の高齢単身者の中では85歳以上の割合が25.6%と高く、高齢女性の単独生活が長期化している現状が浮き彫りになりました。
所得面では、全世帯の平均所得金額は536万円となり、前年の524万2千円から増加しました。児童のいる世帯に限ると平均所得は820万5千円、高齢者世帯では314万8千円という結果が出ています。世帯構成によって大きな格差が存在していることが確認でき、特に高齢者世帯の所得の低さは、老後の生活設計や福祉政策の強化を求める声につながる可能性があります。また、所得の中央値は410万円で、平均所得よりも下回る世帯が全体の61.9%に上るなど、経済的格差の存在も浮き彫りとなりました。
生活意識に関する調査では、自らの生活を「苦しい」と感じている世帯が約6割に達しており、経済的な困難を抱える家庭の多さが伺えます。この「苦しい」は「大変苦しい」と「やや苦しい」の合計で構成されており、幅広い層において生活の余裕のなさが問題視されています。物価上昇や住宅費、教育費などの負担が影響していると考えられます。
児童のいる世帯のうち、母親が何らかの形で就業している割合は80.9%と過去最高を更新しました。就業形態は非正規が36.7%、正規雇用が34.1%、その他が10.1%となっており、母親の働き方にも多様性が見られる一方で、依然として不安定な雇用形態に置かれているケースも少なくありません。仕事と育児の両立に加え、経済的理由から働かざるを得ない母親の現状が読み取れます。
世帯の全体像を年代別に見ていくと、昭和61年(1986年)当時と比べて、世帯構造や平均世帯人員は大きく変化しています。1986年の平均世帯人員が3.22人だったのに対し、2024年では2.20人と1人以上減少しています。この数字の推移は、少子化と単独世帯化が進んできた社会背景を如実に表しています。夫婦のみの世帯や一人親世帯の割合が増加し、三世代世帯や大家族は年々減少しています。世帯構造の多様化は、住宅や福祉、保育政策においてきめ細やかな対応が必要であることを意味しています。
一方で、児童のいる世帯の数は長期的に減少傾向にあり、1986年の時点では1736万4千世帯であったのに対し、2024年では907万4千世帯と約半数にまで減少しました。これは出生数の減少とリンクしており、持続可能な社会保障制度を維持するためには喫緊の課題といえます。さらに、児童の数別にみると、1人の子どもを持つ世帯が47.7%、2人が39.2%、3人以上が13.1%と、少子化の現実を数字が裏付けています。
このように、今回の国民生活基礎調査は、我が国が抱える多くの社会課題を反映しています。高齢化、単独世帯の増加、子育て世帯の減少、所得格差の拡大、生活意識の低下など、今後の政策検討において注目すべき指標が多数盛り込まれていると言えるでしょう。特に企業の採用担当者にとっては、求職者の家庭環境や生活状況により柔軟な働き方を提案する必要があるなど、労働環境整備への示唆も多く含まれています。今後の採用戦略や人材育成において、こうしたデータに基づいた対応が求められる時代が到来していることは明白です。
⇒ 詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ