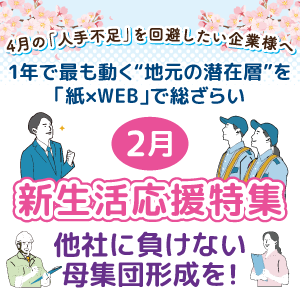2025年5月20日
労務・人事ニュース
生涯医療費は平均2,800万円、85%が保険給付で賄われる日本の医療制度の実態
エラー内容: Bad Request - この条件での求人検索結果表示数が上限に達しました
医療費の見える化について(厚労省)
日本の医療保険制度は、世界的にも高水準の医療サービスを広く国民に提供しており、全ての人が平等に医療を受けられる仕組みが整っています。しかし、こうした制度を持続可能なものとして維持するには、制度の仕組みや財源構成に対する国民の理解と関心が不可欠です。厚生労働省ではそのような観点から、「医療費の見える化」を目的とした情報公開を令和2年度より継続して行っており、令和4年度版では最新の医療費構造や財源の内訳、生涯医療費などがグラフ付きでわかりやすくまとめられています。
まず、医療費の財源構成を見てみると、病院などの医療機関で実際に支払われる医療費のうち、私たちが窓口で負担している「自己負担額」は、平均して全体の約15%に過ぎません。残りの約85%は、医療保険制度を通じて支払われています。この85%の給付を「実効給付率」と呼び、この割合は年齢や制度改正によって変動することが知られています。令和4年度のデータでは、この実効給付率が85.2%となっており、過去10年間で安定的に上昇していることが確認されています。
さらに、この実効給付率の内訳に目を向けると、保険料によって賄われる部分が約53%、国や自治体からの公費によって支えられている部分が約32%であることが明らかになっています。つまり、国民が支払う保険料だけでは全体の医療費をカバーできず、3割以上が税金などの公的資金によって支えられているという実態があります。これは、年齢構成の変化や医療ニーズの多様化といった要因が重なった結果であり、特に高齢化の進展に伴い、後期高齢者への医療支出が急増していることが背景にあります。
実際に、後期高齢者(75歳以上)における自己負担額は全体の医療費のうち約8%とされており、それ以外の年齢層では約19%となっています。この差は、年齢に応じた法定給付率の違いや、高額療養費制度などの支援制度によって生じているものです。高齢者の医療費は一般的に高額になる傾向があるにもかかわらず、自己負担を抑える仕組みが整えられているため、生活の質を維持したまま必要な医療を受けられる環境が確保されているのです。
また、医療保険制度には財政的な調整メカニズムも設けられており、各制度間で年齢構成や医療費水準の違いによる負担格差を是正するための仕組みが働いています。たとえば「前期高齢者調整」や「後期高齢者支援金」といった財政調整制度がそれにあたります。これにより、比較的若い加入者が多い制度が、高齢者比率の高い制度を支える形になっており、全体として安定した制度運営が可能となっているのです。
次に注目すべきは、「生涯医療費」という指標です。これは、その年に生まれた0歳児が平均して生涯に必要とする医療費を示したもので、令和4年度の試算によると、平均で約2,800万円となっています。このうち約2,300万円が医療保険からの給付によって賄われ、自己負担額は約500万円に相当します。医療費の85%が保険給付でカバーされているという構造がここでも確認される一方で、この金額が全ての国民に必要とされることを考えると、医療制度がいかに大規模な支出構造の上に成り立っているかがよくわかります。
さらに、「余命にかかる医療費」という視点からの分析も行われています。これは、ある年齢に達した人がその後に必要とする医療費を示したものであり、例えば60歳時点での余命にかかる医療費は非常に高額となることが確認されています。高齢期に入ると医療ニーズが急増し、入院や慢性疾患治療の頻度も上がるため、必然的に医療支出が膨らむ構造になっているのです。
これらの情報は、企業にとっても無関係ではありません。特に採用担当者や人事部門においては、福利厚生制度や健康経営の設計において、こうした医療制度の動向を踏まえる必要があります。例えば、社員が加入する健康保険組合が負担する医療給付の実効給付率や、保険料の将来的な上昇リスクを見越した資金計画などは、企業財務にも直結する課題です。また、従業員の健康状態が医療費全体に与える影響を把握し、予防医療や健康管理施策を戦略的に推進することは、長期的には企業の社会的責任を果たすと同時に、医療費抑制にも貢献します。
さらに、超高齢社会を迎える日本においては、働きながら医療を受ける高齢者が今後ますます増加することが予想されており、企業には多世代労働力を支える柔軟な就業制度や、医療・介護との両立支援策が求められる時代になっています。こうした視点から見ても、厚生労働省の「医療費の見える化」は、単なる情報公開にとどまらず、企業経営にとっても価値ある資料であることは間違いありません。
制度の持続可能性という観点では、医療費の安定的な財源確保は国家レベルの課題ですが、企業や個人が制度への理解を深め、適切に制度を利用していくことも極めて重要です。現役世代の負担が重くなる中で、公費と保険料、そして自己負担のバランスをどう取るかが、今後の政策課題として浮上しています。医療保険制度は国民全体の合意と協力のもとに支えられているものであり、制度の構造を知り、自らの役割を理解することが、持続可能な社会保障を築く第一歩となるのです。
⇒ 詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ