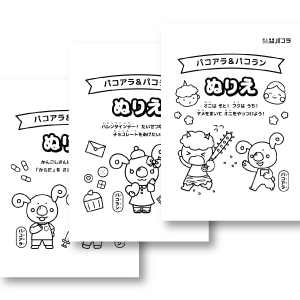2025年4月22日
労務・人事ニュース
1戸あたり最大200万円補助、空き家を福祉住宅に再生する新制度始動
- 歯科衛生士 幅広い年齢層の患者さまが訪れる地域密着型の医院です
最終更新: 2026年2月1日 21:30
- 歯科衛生士 安全と清潔にとても気を遣った快適な歯科医院です
最終更新: 2026年2月1日 21:30
- 歯科衛生士 駅チカ4分/マイカー通勤OK 残業少なめでメリハリのある働き方叶います
最終更新: 2026年2月1日 21:30
- 歯科衛生士 衛生士さんにとって働きやすい環境が整ってます 週1~OK、充実した教育制度
最終更新: 2026年2月1日 21:30
空き家等を改修してセーフティネット住宅とする事業者を支援します! ~「令和7年度 セーフティネット専用住宅改修事業」の募集を開始~(国交省)
令和7年4月2日、国土交通省住宅局安心居住推進課より「令和7年度セーフティネット専用住宅改修事業」の募集が開始されました。この取り組みは、空き家や民間の既存賃貸住宅などを改修し、住宅確保要配慮者向けの住まいとして再生する事業者を支援するものであり、住宅セーフティネット制度の枠組みの中で、住まいに困る人々が安心して暮らせる住環境を整備することを目的としています。空き家問題の解決と住宅困窮者の支援という二つの社会的課題に対応する本事業は、地域社会の活性化と福祉の向上を両立させる重要な政策です。
対象となるのは、低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯など、住宅の確保に特別な配慮が必要とされる住宅確保要配慮者です。これらの方々が安心して住み続けられる住宅環境を提供するために、国は改修工事に対して1戸あたり上限50万円の補助金を支給します。補助率は原則1/3とされており、バリアフリー化や耐震補強、子育て支援設備の設置など、具体的な改修内容によってはさらに上限額が加算される仕組みになっています。
補助対象となる工事は多岐にわたっており、たとえば外構部分を含むバリアフリー改修、地震に備えた耐震補強、複数人の共同居住が可能となる間取り変更、子育て世帯向けの対応工事、防火対策、住民交流のためのスペース設置、省エネルギー化改修、見守りや安否確認設備の導入、防音・遮音対策などが挙げられます。特にエレベーターの設置や、車椅子使用者に配慮したトイレや浴室の整備などを行う場合には、最大で100万円までの補助が可能となります。また、子育て支援施設を併設するケースでは、1施設あたり最大1,000万円の補助が設定されており、住宅単位だけでなく、施設全体の整備に対する支援も充実しています。
今回の募集においては、既にセーフティネット住宅として登録済みの物件に対しても一部の改修項目について補助対象とする柔軟な対応が取られています。特に、IoT技術を活用した安否確認設備の導入や、地域交流を促進する共用スペースの設置、防災に備えた設備改修などについては、すでに運用中の住宅でも補助対象となるため、今あるストックを有効に活用しながら、住環境の質を向上させることが可能となっています。
さらに、この制度は単なる住宅のハード面の整備にとどまらず、入居者の暮らしを支えるためのソフト面にも配慮がなされています。例えば、改修に伴う調査設計費用や、居住支援法人による見守り活動の運営に必要な準備費用なども補助対象とされており、居住支援の仕組みづくり全体を包括的に支援する構造になっています。また、工事期間中の仮住まいに必要な家賃補助(原則3か月分、要件を満たせば最大1年間)まで含まれており、入居者の生活が途切れることなく継続できるよう細やかな配慮が施されています。
この改修支援の応募には、令和7年12月12日までに交付申請を完了させる必要があります。また、同日までに事前審査願も受け付けており、事前審査を受けた事業者であっても、正式な交付申請書類の提出がなければ補助の対象とはなりません。応募手続きは電子メールでの申請が基本とされており、事業に関心のある事業者は所定の事務局へ必要書類を送付することで申請を行います。
対象となる住宅にはいくつかの条件が設けられており、たとえば家賃は公営住宅に準じた水準以下であること、近隣の同種住宅との価格バランスを保つことなどが要件として挙げられています。また、登録された専用住宅については、最低でも10年間の管理期間が求められており、長期にわたり住宅確保要配慮者のために提供されることが前提となっています。ただし、一定の条件を満たす場合には、要配慮者以外の入居が認められる柔軟な運用も可能とされています。
このような支援制度は、空き家を有効活用しながら社会的弱者を支える仕組みとして注目されており、特に地方自治体や中小の不動産事業者にとっては、地域課題の解決と事業拡大を同時に実現できる好機となります。加えて、災害時の被災者受け入れ住宅としての事前登録も推奨されており、防災・減災の観点からも活用が期待されています。
企業の採用担当者にとっても、この制度の活用は自社の社会的責任(CSR)の観点から重要な意味を持ちます。特に福利厚生の一環として、社員の家族や親が安心して住める住宅を地域内に確保しておくことは、社員の離職防止や就労継続の支援に直結します。また、住宅・建設業界の企業にとっては、新たな市場参入のきっかけとして、あるいは既存資産の有効活用の手段として、この制度をビジネスモデルに組み込むことも現実的な選択肢です。
⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ