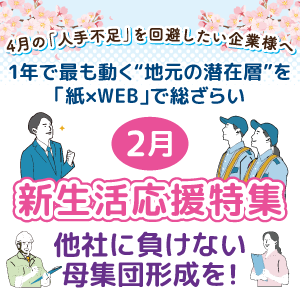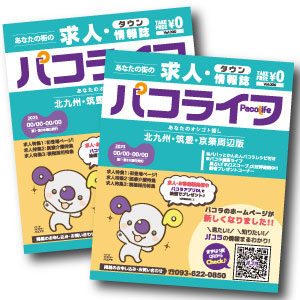2025年9月3日
労務・人事ニュース
2024年のトラフグ漁獲量が過去最低の131トン、資源評価結果が明らかに
- 訪問看護業務/即日勤務可/シフト
最終更新: 2026年1月22日 01:06
- 訪問看護師/高時給/即日勤務可
最終更新: 2026年1月22日 01:06
- 常勤・医療業界の看護師/車通勤可/即日勤務可/シフト
最終更新: 2026年1月21日 09:35
- 常勤・医療業界の看護師/残業なし/即日勤務可/土日祝休み
最終更新: 2026年1月22日 01:06
令和7年度我が国周辺水域の水産資源に関する評価結果が公表されました(トラフグ日本海・東シナ海・瀬戸内海系群)(水産庁)
この記事の概要
2025年8月19日、水産庁はトラフグの日本海・東シナ海・瀬戸内海系群に関する令和7年度の資源評価結果を公表しました。報告によれば、トラフグの漁獲量は過去最低水準に落ち込みつつも、親魚量は増加傾向にあり、資源管理の成果が一部で見られることが分かりました。今後の漁獲管理方針や放流対策に関する見通しも示され、持続可能な水産資源の確保に向けた取り組みが求められています。
国立研究開発法人水産研究・教育機構が実施する全国の水産資源評価の一環として、2025年8月19日、トラフグの日本海・東シナ海・瀬戸内海系群に関する令和7年度の評価結果が公表されました。これは、全国で調査対象となっている192魚種の中のひとつで、特に我が国沿岸漁業にとって重要な位置を占めるトラフグの最新の資源状況を示すものです。今回の評価は、持続可能な漁業の実現に向けて、今後の管理方針の策定や資源保護施策に活用される重要な基礎資料となります。
対象となるトラフグ系群は、秋田県から鹿児島県に至る日本海や東シナ海沿岸、さらに豊後水道や瀬戸内海、有明海といった内湾域にも広く分布しており、加えて中国や韓国など東シナ海沿岸国にも生息域を持つ広域的な魚群です。この系群では1977年以降、人工種苗の放流が行われており、資源維持への対策が続けられています。
しかしながら、近年の漁獲状況には課題が残ります。特に2024年漁期における漁獲量は131トンと、2002年漁期の363トンから大幅に減少しており、記録上過去最低の水準となりました。一方で、資源量自体は2024年漁期で941トンと依然として一定の水準を保っているものの、2021年以降は緩やかな減少傾向が続いています。漁獲割合も低下を続け、2024年漁期には14%にまで下がりました。
年齢別の漁獲状況を見ると、特に若齢魚の割合が低下傾向にある点が顕著です。2024年漁期では、4歳以上の成魚の漁獲が最も多くを占めており、資源の若返りが十分に進んでいないことが示唆されています。このままでは長期的な資源再生産能力の低下が懸念されるため、今後の加入状況の回復が重要な課題となります。
加入量については、2005年漁期の82万尾をピークに長期的な減少傾向が続いており、2024年には11.3万尾まで落ち込みました。そのうち、天然由来の加入量は8.8万尾、人工放流由来は2.5万尾という結果で、全体的な資源の補充力が著しく低下している状況です。
一方で、親魚量に関しては2002年以降緩やかに増加しており、2024年漁期には702トンと評価されています。これに基づき、今後の資源管理方針においては、F30%SPR(親魚量が漁獲なしの30%残る水準)を漁獲圧の目安とし、最大持続生産量(MSY)の代替指標として191トンの漁獲量を基準とする方針が示されています。親魚量の目標管理基準値は577トンとされ、2024年の実績はこの基準を上回っており、資源の一定の健全性が保たれていると評価されます。
また、将来的な漁獲管理の在り方としては、現行の漁獲圧を維持しつつ、β=0.7の管理係数を用いた場合、2036年には親魚量が目標値を上回る確率が24%である一方で、βを0.4に設定した場合にはその確率が50%を超えると予測され、より厳格な管理が効果的であるとされています。
さらに、人工種苗の放流による効果も分析されています。2019~2023年の平均放流尾数149.8万尾を基に計算された添加効率は0.045とされ、資源加入への貢献尾数は6.7万尾と推定されました。これを加味した予測では、β=0.7とした場合でも2035年には親魚量が目標基準値を上回り、2046年には漁獲量がMSYを超えると見込まれています。
今回の評価結果は、科学的根拠に基づいた資源管理の必要性を改めて示しており、今後の政策決定においても、データに裏打ちされた持続可能な漁業モデルの構築が求められます。漁業従事者や行政関係者、研究機関が一体となり、長期的視点に立った管理と調整を進めていくことが不可欠です。漁業資源の安定供給を確保し、食料安全保障にも貢献するためには、より一層の科学的な評価とその活用が必要とされます。
この記事の要点
- トラフグの漁獲量は2024年に131トンと過去最低を記録
- 親魚量は増加傾向で2024年には702トンを記録
- 天然由来の加入量は2005年の75.4万尾から2024年には8.8万尾に減少
- 放流由来の加入量は2024年に2.5万尾
- 資源量は2024年に941トンで漁獲割合は14%
- β=0.7の漁獲管理で2036年の目標達成確率は24%
- 放流を加味した管理では2035年に親魚量が目標値超えの見通し
⇒ 詳しくは水産庁のWEBサイトへ