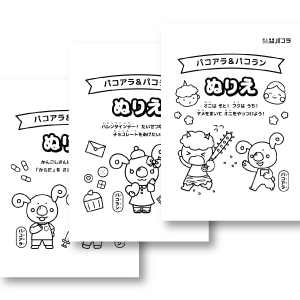2025年7月19日
労務・人事ニュース
雇調金の受給企業が最大18%に達したコロナ特例、早期は効果大も長期利用で逓減傾向
- 歯科衛生士 地域密着型の歯科医院で患者様の笑顔を見よう
最終更新: 2026年2月1日 21:30
- 歯科衛生士 薬院駅すぐ 退職金あり 教育制度充実 CT完備の歯科医院で衛生士を募集しています
最終更新: 2026年2月1日 21:30
- 歯科衛生士 駅チカ 高待遇 社保完備 マニュアル完備 帰りは早め 教育も充実
最終更新: 2026年2月1日 21:30
- 歯科衛生士 社会保険完備 最新の設備で歯科衛生士として新しい一歩を踏み出しましょう
最終更新: 2026年2月1日 21:30
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う 雇用調整助成金の特例措置の効果検証に関する研究(JILPT)
2025年6月30日に発表された労働政策研究報告書No.236では、新型コロナウイルス感染症の影響下で実施された雇用調整助成金の特例措置(いわゆるコロナ特例)について、実際にどのような効果があったのかを精密に検証することを目的とした研究の成果が明らかにされました。今回の研究では、雇用保険の業務データと事業所アンケート調査を組み合わせたデータセットを用い、特例措置が当初想定された役割を果たしたかどうか、企業や労働者、さらには労働市場全体に対する影響まで幅広く分析されています。
まず注目すべき点は、コロナ特例による雇調金の支給規模が、過去の経済危機と比較しても極めて大きかったことです。例えば、2008年のリーマンショック後には2010年に受給事業所の割合が5.0%にとどまっていたのに対し、今回のコロナ禍では2020年に約18%、2021年に約14%、2022年でも約10%の事業所が受給しており、支援の範囲と深度がいかに拡大していたかが数字からも明らかです。これにより、多くの企業が雇用を維持するための時間的猶予を得ることができたと考えられます。
雇調金の効果については、特に支給初期において顕著な雇用維持効果が認められた一方、利用期間が長期に及ぶにつれて、その効果は逓減する傾向にありました。とりわけ、教育訓練を活用した場合には早期段階での実施による効果が高かった反面、コロナ後期での訓練実施では雇用維持への寄与が限定的であることも判明しています。
また、雇調金を受給していた事業所の離職者は、非受給事業所の離職者と比べて再就職にかかる時間が長い傾向にあり、これは制度によって一時的に雇用が維持された反面、中長期的なキャリアの転換や再構築に向けた支援策の必要性を示唆しています。非正規雇用者向けの支援として導入された緊急雇用安定助成金についても一定の効果は見られたものの、雇調金に比べるとその効果は限定的であり、今後の制度設計においては小規模企業や非正規労働者に対するより柔軟で持続的な支援策が求められるとしています。
事務手続きの面では、制度導入当初より簡素化が図られており、また制度の周知も概ね適切に行われたことが報告されています。しかしながら、助成率や上限額といった特例措置の個別の効果については定量的な検証が難しく、将来的な政策評価に向けたデータ整備の重要性が指摘されています。特に、今後も緊急時に迅速かつ的確に支援制度を運用するためには、平時からのデジタル化推進、データ項目の整理、他の業務データとの接続性の確保などが不可欠です。
さらに、雇調金の受給が終了した事業所のうち、およそ15%が廃業していたことも確認されており、支援終了後の経営安定性をめぐる課題も浮き彫りとなりました。とくに、受給終了時点が後期にあたる事業所ほど、廃業までのスピードが早い傾向があることは、支援の出口戦略や中長期的な経営支援の在り方を再考する必要性を示しています。
本研究成果は、厚生労働省の労働政策審議会でも速報として共有され、今後の雇用調整助成金制度における政策立案の基礎資料として活用されることが期待されています。今後の緊急事態においても、制度が迅速かつ的確に機能し得るよう、持続可能で柔軟な制度設計が求められます。企業の人事・総務部門にとっては、今後の支援制度活用に関する知見を得るうえで本報告書は重要な示唆を与えるものといえるでしょう。
⇒ 詳しくは独立行政法人労働政策研究・研修機構のWEBサイトへ