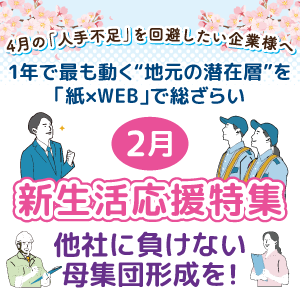2025年10月21日
労務・人事ニュース
母子世帯のうち約40%が祖父母と同居、育児と生活の実態
エラー内容: Bad Request - この条件での求人検索結果表示数が上限に達しました
ひとり親世帯における多世代同居の階層性 ―『国勢調査』個票データを用いた分析―(社人研)
この記事の概要
国立社会保障・人口問題研究所による最新の分析では、ひとり親世帯における多世代同居の実態に焦点を当て、『国勢調査』の個票データを用いてその階層性に関する構造的特徴が明らかにされています。特に、母子世帯と父子世帯の間での違いや、同居形態がもたらす経済的・社会的背景との関連性に注目した研究です。
本研究は、ひとり親世帯における多世代同居の実態と、その背後にある階層性を統計的に検証したものであり、『国勢調査』個票データを用いた実証分析によって、その社会的背景に踏み込んでいます。研究では、同居の有無や同居の種類(直系親族との同居、きょうだいとの同居など)によって、世帯の属性や生活状況に違いがあることを明らかにしており、特に母子世帯と父子世帯の間に明確な差が見られました。
調査の結果によれば、多世代同居をしているひとり親世帯の多くは、経済的な理由から家族との同居を選択している傾向があることが示唆されました。特に、母子世帯では同居率が高く、子育て支援や家計の安定を目的とする側面が強く見受けられます。一方で、父子世帯では同居率は比較的低く、個人としての自立志向が反映されている可能性があることが指摘されています。
また、同居している世帯は、単独で生活しているひとり親世帯に比べて、持ち家率が高い、就業状態が比較的安定している、学歴が高いといった特徴が見られました。これは、同居している世帯がより高い社会経済的地位にある可能性を示しており、「多世代同居=経済的困窮層」という単純な図式では捉えきれない構造が存在することがわかります。
一方で、生活保護の受給率や非正規雇用の比率が高いなど、経済的に厳しい条件下にある世帯ほど、家族との同居に頼らざるを得ない状況も浮き彫りになっています。つまり、多世代同居は一部では経済的セーフティネットとして機能しており、日本における非公的扶助の一形態とも捉えることができます。
さらに分析では、同居の有無と地域性との関係にも着目しており、地方圏では同居率が高く、都市部では低いという傾向が確認されました。このことは、住宅事情や地域の家族文化、支援体制の違いが影響している可能性を示唆しています。また、都市部においては保育サービスや就労支援が比較的充実していることから、親族と同居せずとも子育てや生計を維持しやすい状況がある一方で、地方では同居による相互支援が生活の安定に大きく関わっていると考えられます。
本研究は、家族構成の多様化や貧困問題、地域格差といった複数の社会課題が複雑に絡み合うなかで、ひとり親世帯の現実に即した政策設計の必要性を訴えるものであり、住宅政策や雇用支援策、育児・介護のサポート体制において、多世代同居の機能と課題を正しく理解し反映させることの重要性を示しています。
この記事の要点
- 国勢調査個票データを用いてひとり親世帯の多世代同居を分析
- 母子世帯の同居率は父子世帯よりも高い
- 多世代同居は経済的支援や育児支援の側面が強い
- 同居世帯は学歴や持ち家率などで相対的に高い社会経済的地位を有する
- 非正規雇用や生活保護世帯では同居によるセーフティネットが重要
- 都市部より地方での多世代同居率が高く、地域差も大きい
- 住宅・雇用・子育て支援政策に多世代同居の視点を取り入れる必要がある
⇒ 詳しくは国立社会保障・人口問題研究所のWEBサイトへ